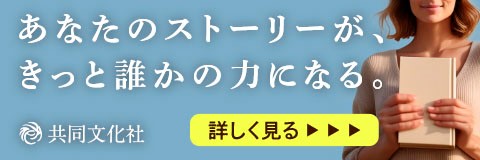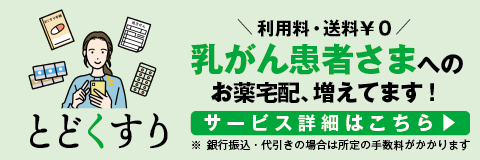第33回日本乳癌学会学術総会報告 ②-2

左から、牧野葉子(神奈川)、西貝圭子(ピンクリボン練馬)、栗原みどり(栃木)
川野紀子(兵庫)、草野安子(栃木)
【3日目】これからの患者は多岐にわたって医療に貢献する時代
午前中は治療に大切な講演内容でした。午後からは一段とレベルアップして「臨床試験」について学び、その後の学びの広場では参加希望をして選ばれた50人が被検者になったと想定して、与えられた情報・課題に基づいて「この臨床試験に参加するかどうか」をグループごとに議論し合って発表しました。
これからの患者は医療に対するPPI(患者・市民参画)や倫理委員会に召集されたり、患者向けのガイドライン作成に委員として選ばれたり、多岐にわたって医療に貢献する時代が来たのだと実感しました。
ここでも、以下のテーマでの話がありました。
◆「乳がん転移再発後の薬物治療」
◆「乳がん転移再発後:骨転移の治療戦略」
◆「臨床試験」
イメージとしては、再発治療をしていて、もう使える薬がなくなったので藁をも掴む思いで参加するものだと思っている人が多くいますが、そうではありません。今やファーストラインでも使う薬の臨床試験もあることが分かりました。
薬が私たちの手元に届くまでには長い道のりがあることや説明同意文章には何が書いてあるのか等を詳しく教えられた。臨床試験は、治療のためではなく、新たな治療方針の確立のために行なわれるもので、未来に繋がる研究の懸け橋なのだということと理解しました。
◆学びの広場「この臨床試験、あなたなら入りますか?」
希望者から選ばれた学びに意欲のある人たちが参加し、再発、HER2陽性乳がん患者になりきって「標準治療+プラセボ」群と「標準治療+注射の上乗せ」群で効果判定をする臨床試験に参加するかどうかを考えるというもの。
想定される副作用や日常生活におけるQOLを考えて判断を下すという選択に挑戦した。患者間でもいろんな意見や価値観の違いを垣間見ることができました。
【3日間を通しての感想】
▼初日のBC-PAPラウンジは若手ドクターやコメディカルに開放されていましたので、一人で【あけぼの会】宣伝のロビー活動をしました。手作りの名刺にQRコードを付け、スマホで読み取ると会のHPにリンクするようにしました。直ぐにHPを見て下さっていたので、会を知ってもらうきっかけになったと思います。
▼学会に参加されている先生方の顔ぶれもすっかり変わり、私が罹患した20年近く前の先生方は第一線から退かれていて、演題発表は若手ドクターが目立ちました。懐かしのお顔を見つけても、座長の大役を務められている場面ばかりでした。ですが、いろんな研究の中心になって活躍中の女性ドクターが多くおられて、女性医師が増えることは患者にとっては、ありがたく心強く思いました。
▼また患者も先生方に交じって登壇し発表をしました。「再発・転移の乳がん患者のサバイバーシップ」では、2年半前に転移の告知を受けて絶望だったけれど、今はもうその絶望の中にはいない。仲間に支えられて、毎日を過ごせていることに感謝する日々で、これが自分の持っていたレジリエンスだったと気が付いた。
下から見える坂道を登り切ったところは崖ではなくて、その先はまだ緩やかな坂道が続いていることが分かったので、これからも歩き続ける、と力強く語られたことに強く感銘を受けました。
▼3日間の乳癌学会学術総会は実り多い学びの日々でした。患者交流会では、今年もまた新たな出会いもありました。お互いに尊敬し合える患者会の仲間もたくさんできたので、とても嬉しく、充実感でいっぱいです。