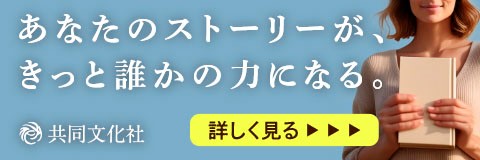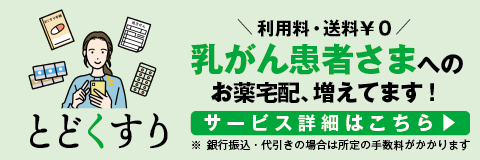第33回日本乳癌学会学術総会報告 ②-1
川野紀子(副会長、あけぼの兵庫代表)

永橋昌幸先生(兵庫医大)と片岡明美先生(がん研有明病院)を囲んで
左端・栗原みどり(栃木)、川野紀子(兵庫)、牧野葉子(神奈川)3代表
日時:2025年7月10日(木)~7月12日(土)
会場:新宿京王プラザホテル・工学院大学新宿キャンパス
大会テーマ:「アジアと欧米の違い」
【1日目】「乳がん検診/診断の現状とリスク層別化乳がん検診の取り組み」
日本は諸外国に比べてマンモグラフィ検診率がかなり低いことが指摘された。それなのに高濃度乳房の占める割合は、反対に日本が欧米に比べて、はるかに多いことが分かった。高濃度乳房は乳がん発症リスクが2倍あり、雪の中の白兎を見つけにくいのと同様に、がんを見つけにくく見逃してしまうことがある。
そういう場合、アメリカではMRIが有効であるとして、MRIできちんと調べる。が、日本は、超音波検査を実施すればいいとされてはいるが、検診の段階では見送られている。
欧米は乳がんになるリスクが個々によって違うことから、リスクの層別化をして、サーベイランスを行い、ハイリスクの20%の人には有効なリスク低減手術をしたり、2次予防のサーベイランスを行ったりしている。 高濃度乳房の検診のあり方は今後の日本の課題です。
◆アジアと欧米の違いー「人工物乳房再建」について
日本では2013年にインプラントが保険適用になったので、この年から全摘乳房再建が急激に増加している。日本は人工物再建と自家組織再建率が6対4で、再建率はアメリカや韓国よりもまだかなり低い。術式は、日本は大胸筋下に挿入することが決められているがアメリカや台湾、韓国では皮下留置が主流。その術式では術後の痛みが少ないのと回復が早いというメリットがあるとの説明でした。また台湾や韓国では左右の乳房のバランスを保つために対側乳房も手術することも多いそうですが、日本はしない。
◆「どこまでガイドラインに従うべきか」
ガイドラインに従った治療の有用性は言うまでもないが、臨床試験の結果と実際に臨床に関わっていると、違った場面に出くわすことも多くある。患者さんのQOLや医療経済を考えると、エビデンスを対象者全体に当てはめるのがいいのかどうかを中間リスクの全摘患者の放射線治療やCDK4/6阻害薬を使ったソニア試験を例にとって考察していき、最後にディスカッションをしてみんなで考えていくものでした。
臨床のデータは重要でエビデンスを確立するのに10年近くかかる。またガイドラインは過去のデータから作るものなので、やはり時代にそぐわないものもある。またデータの殆どが海外のものなので、日本のデータも大切で必要である。
CDK4/6阻害薬は、とても有効でいい薬ですが、ファーストラインから使ってもセカンドラインから使っても効果に差がなかったので、それなら、ファーストラインから使わずに経済毒性を考えて従来の安価な薬剤から使って行くのが好ましいのではないか。
今後の乳がん治療は個別化治療になっていくので、ガイドラインは治療指針にはなるけれど、それに縛られることなく、臨機応変に対応していく――これが各国とも共通した見解に至っている。

石川 孝先生(東京医科大学・乳腺科学分野)
とツーショット、立派!この度胸!
【2日目】BC-PAPが始まりました
東京開催ということもあって、神奈川の牧野代表・栃木の栗原代表と会員の草野さんも参加、全員合流して、みんなで楽しく学びました。
アドボケーターだけではなく治療中の患者さんやご家族も多数来られていて150人を越える現地参加者。 乳がん患者として学んでおくべきことを多方面からアプローチされたプログラムだったので、患者としてはBC-PAPだけの参加でも充分学べたと思いました。
今回はタブー視されがちな、でも人として大切な乳がん治療において抱えるセクシャリティーの問題まで踏み込んだ画期的な内容のプログラムもありました。
◆「アピアランスケア」
外見を良く見せる、綺麗になるのが目的だけでなく、がん罹患後も「自分らしく社会生活を送ること」を支援するケア。患者さんの心理的・社会的側面を踏まえてケアを提供することが必要で、そのためにウイッグや補正下着があるのであってその情報を単に伝えるのがゴールではないことを強く言われていました。
他に以下のテーマで話が進みました。
◆「患者の経験を生かすがん教育」
◆「乳がんのドラッグラグ・ドラグロス」
◆「乳がん周術期の薬物治療」
◆「手術、再建から下着問題、パートナーシップまで」