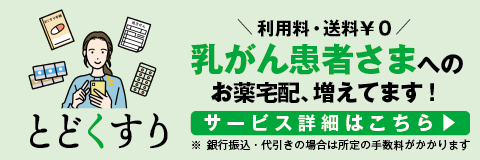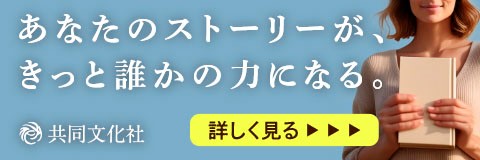「再発と生きるということ」

(バックは駒ヶ岳・2025/10/29)
撮影:久保玲子(北海道)
💛私が、乳がんで、それも腋下リンパ節に2個転移していると告げられて、初期ではなく2期だと雑誌で見て、5年生存率が75%と分かったとき、「死」が頭の中に刻み込まれた。5年以内に再発が起きて、死んでしまう、ということなのだ。37歳だったので、42歳までしか生きられない、娘は7歳、息子は4歳、それぞれ12歳と9歳までしか見られない、もう絶対に死ぬことに決めてしまっていた。
💛当時は、がんを告げるべきか否かを議論していた時代なので、患者は殆ど情報が得られなかった。私は、まず「死にたくない」、でも、死には勝てない、仕方がない、「どうしよう」、パニックになって、精神科を受診したり、電車に乗って、遠くの知り合いに会いに行って、気持ちを話してオイオイ泣いたりした。そんな時、「ほかの患者はどうしているのだろう、みな不安なはずなのに」と気づいて、新聞に投書した。
💛「同じ体験をして、同じ思いの人は集まりましょう」投書に反応して集まった人たち17人で「あけぼの会」が誕生した。1978年10月のこと。全国から怒涛の如く人が集まり、私の不安はいつの間にか消えて、会長の仕事が始まった。みなが同士を求めていた。
💛47年経って今、世の中が変わった。がんを告知されても、すぐに「再発」「死」を必ずしもイメージしない。「再発そのものより、再発したときに生活をどう建て直したらいいか」を心配していると言う。患者は強くなったのだろうか?
💛しかしながら、がんには再発があるのが事実である。これが他の病気と違うところで、その不安を抱えて生きていくからこそ、患者会が必要で、盲腸の患者会は必要ない。死の不安などないからだ。
💛【あけぼの会】でも大勢の同士を失った。再発に勝てなかったのだ。今も再発闘病している会員があちこちにいる。けなげに、何もなきが如くに振る舞い、生きている。そんな人の精神はどうなっているのか、知りたい。強靭な精神力は何に裏付けされているのか?
💛【あけぼの東京】の12月のメインテーマがこれ。二人の再発治療中の会員に話をしてもらう。新潟の内藤桂子さん(68)といわきの木村智子さん(55)、共に仕事を持ちながら、長い間、再発と闘っている。今回お願いしたら、二人とも快く引き受けてくれた。木村さんは学校の先生なので、闘病記録のスライドも持って来てくれる。二人の生きざまから、何を学ぶか、今度はこっちが試されるだろう。心して、聞こう。(詳細はTopicsに)
(ワット)