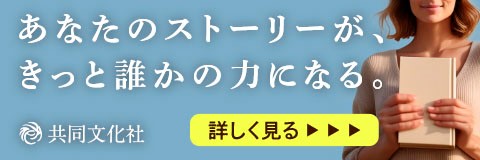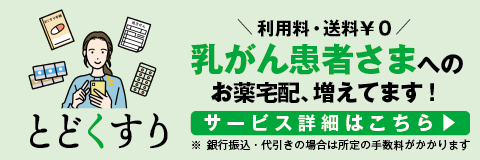第26回日本乳癌学会学術総会(2018/5/16~5/19)に参加して
《2018年5月23日更新》
 学会参加の滋賀メンバー(総勢11名・右から5人目・菊井代表)(2018/05/18)他に、福岡、山口、愛知、岐阜、兵庫、奈良、大阪から代表さん他が参加しました《菊井津多子・あけぼの会副会長/滋賀代表のリポート》
学会参加の滋賀メンバー(総勢11名・右から5人目・菊井代表)(2018/05/18)他に、福岡、山口、愛知、岐阜、兵庫、奈良、大阪から代表さん他が参加しました《菊井津多子・あけぼの会副会長/滋賀代表のリポート》
●5月16日から第26回日本乳癌学会学術総会が京都で開催されましたので参加しました。メインテーマは「Creative Japan新たな時代」。偶然にも学術総会開催年数は私の術後年数と同じ。再発時に命を少しでも永らえたいと切望した新薬や治療が現実となっている今日、さらに高みを目指している学会のスピード感に驚き、そして期待と希望を感じました。
●18日のプログラム「明るいサバイバーシップを目指した若年性乳がん患者の診療」では、妊孕性、妊娠時の乳がん等、目新しい発表が続き、若年性乳がん患者団体の患者対象アンケート調査の発表では、患者会が乳がん患者の精神的サポートの役割を果たしているとあり、改めて、私たちの活動である「あけぼのハウス」の意義を再確認しました。「再発リスクに応じた周術期乳がん治療戦略」MDアンダーソンがんセンターの上野直人医師の講演では、会場の医療者が、患者さんのプロファイルに基づいて、提示された幾つかの薬物療法をアナライザーで選ぶと瞬時に結果が出る方式で、そこで出た違いに、日本での更なるキャンサーボードの普及、複数の医療者の丁寧な議論の下での治療決定がなされてほしいと痛感しました。「医療者は患者に治療法についてしっかりした説明をしないといけない」という上野医師から日本の医師へのメッセージがあり、拍手!知識は患者の力になりますが、知識を医療者と共有して初めてその力が発揮される。重要なことです。
●「乳がんガイドライン」改定の話もあり、17日の新聞各紙に遺伝性の乳がんについて、将来がんになるリスクを減らすため、反対側のがんのない乳房を予防的に切除する手術を「検討してもよい」から「強く推奨する」と学会の診療指針を改定したことが掲載され、大きな反響を呼んでいます。乳がん医療は今や、遺伝子レベルでの予防、治療に大きく舵が切られたと感じた学会でした。
●19日の『患者セミナー』―乳がん克服に向けて立ち上がろう コンサート―にも参加しました。高濃度乳房の話と検診のメリット、デメリットが取り上げられ、私たちの啓発活動に参考になりました。その際発表された「ブレストアウェーネス・Breast Awareness」という概念としての教育にわたしの心は大きく動きました。
●『市民公開講座』では復帰後、初の舞台として藤山直美さんが登場されました。“治療は先生にお任せしています。但し、患者として治療をしている間は治療に支障をきたさないように体調管理をしています”というお話に、まさに患者の本音!同感!と思いました。元気な姿に勇気づけられ、いつもの直美トークに笑い「どうか完治されますように」の思いを込めて、応援の拍手を送りました。