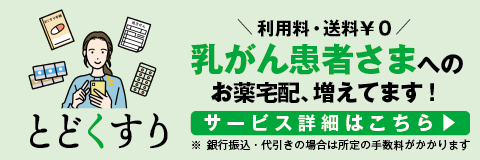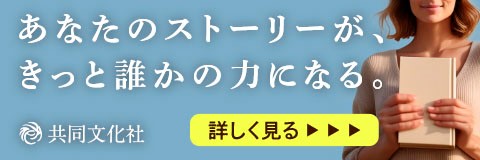自分の命は自分で守る 佐藤清子(あけぼの秋田代表)
《2020年3月4日更新》
 ―-体験と会の活動についてーー
―-体験と会の活動についてーー
秋田県立仁賀保高等学校の 「がん教室」で
(2019/11/19 学校HPより) 【あけぼの会】本部が福岡に移ってから、各県の代表が力を合わせて会を運営していることは、女性学を学んだものとして、ものすごいパワーを感じます。
私は【あけぼの会】に、術後10年経た1990年10月に入会しました。担当の医師でさえ患者会の存在を知らなかった時代、ワット隆子前会長の公開講演会が秋田市で開催されるとの新聞記事を見て、聴講に行ったことがきっかけでした。「手術後も明るく生きること」のメッセージを聞いて、全摘術式の時代、身体的に大きな負担があった中でも、体験者としてなすべき事があると実感し、すぐに入会の手続きをしました。
今年令和2年、術後40年を迎えて、あけぼの会、主治医、看護師、放射線技師、ほか医療者の皆様に感謝です。この繋がりがあったからこそ、今まで生きてこられたとの思いで胸がいっぱいです。
今、乳がん患者会が存在しない県、病院はあるでしょうか? それだけ患者が増加の一途を辿っていて、患者会のニーズがあるのです。
【あけぼの秋田】は、平成9年から公益財団法人秋田県総合保健事業団(日本対がん協会グループ提携団体)の実施事業に協力を依頼され、今年で23年目となります。県内各地で開催の「健康・環境フェスタ」において、「乳房触診モデルによる自己検診体験コーナー」で、私と会員がセルフチェックの指導をしており、県内の方はもちろん他県や外国の方など多くの方に体験していただいています。
「のしろ健康21健康展」や「ピンクリボンin AKITA」の会場では、10歳代~80歳代の幅広い年齢層の方に対して一日で150名にも及ぶこともありました。男性乳がんの発見につながった事例もあります。
ある時、モデルを触って、一生懸命しこりを見つけようとしていた小学生に「将来お医者さんになりたいの?」と尋ねたら、「看護師さん」という返事でした。きっとこの日の体験が医療者の道へと繋がるとの思いを抱かせてくれました。
アンケートのコメント欄には「乳がん検診を受ける」と記入する方が多いです。乳がん検診の啓発活動は、体験者としての私に、そして【あけぼの会】に、大きな役目を与えてくれました。これからもそうでしょう。
また、秋田県教育庁からの依頼で、平成27年度から県内の高校と中学校の「がん教育授業」に体験者として「講話」をしています。ワークショップにも参加して、子供達から「将来は医療に関わる仕事に就きたい」と、嬉しい言葉を聞くこともあります。
【あけぼの会】(あけぼの秋田・代表)として社会に貢献できる自分でありたい。「自分の命は自分で守る。そして、明日への希望をもって生きよう!」という【あけぼの会】のモットーを、これからもずっと世の中に発信していきたいと思います。 佐藤清子 sato-seiko@peach.plala.or.jp