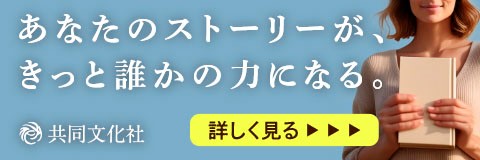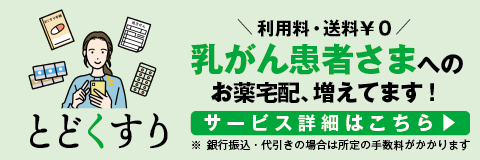VHO-net*九州学習会のオンライン会議に参加しました
深野百合子(あけぼの会会長)《2020年7月29日更新》

撮影:深野百合子 2019/9/8 【あけぼの会】はコロナ禍の影響で、各地で活動の自粛が続いています。そんな中【あけぼの神奈川】ではオンライン交流会を開催。また【あけぼの岐阜】では懇話会の模様をユーチューブで配信するなど、今できることにチャレンジして見せてくれました。
そして私は去る7/18(土)、VHO-net*九州学習会のオンライン会議に参加しました。参加者23名。テーマは「〈実際に集まる〉以外の活動を実践している団体から現状とそこからの気づき」でした。
〈準備〉会議の数日前に「オンライン接続テスト」や「グランドルール(会議中の注意点など)の周知」があり、会議はスムーズに進みました。ただ、当日接続が上手くいかない人もあり、ネット環境や機種、ツールに精通している人が必要と思いました。
〈事例報告〉①オンラインの活用事例を紹介して、「会の活動」にはビジョン(Vision)とミッション(Mission)が最も大切!この状況の中で、今出来ることは何か探し、それぞれ の会にあった活動スタイルを見つけて欲しい。②また、オンライン会議のツール(Line・Skype、Zoom、Teams)の特徴と用途の説明がありました。
〈グループディスカッション〉殆どの団体がオンラインを活用中。感想は、「寝たきりや外出できない会員も参加できた」、「顔を見るだけの人ともオンラインを通じて親しくなれた」、「どこにいても参加できて時間と費用の節約になるが、会議が増えてかえって忙しくなった」、「会議が終わってビール片手に雑談が楽しい」、「アプリで背景を変えて参加した」など。
一方、活用していない会では「コロナまん延の時期に入院していたので、面会も出来ず話す人がいなくてとても寂しく不安だった。病院の要請もあり、毎月『お話し会』を開催している。会って話をすることの大切さを実感した」との意見もありました。
【あけぼの会】も従来の「あけぼのNEWS」の発行や〈あけぼのハウス〉などの活動を大事にしつつ、オンラインを活用して親睦会・勉強会などの導入も必要で、まさに転換期だと確信しました。先ずは、全国代表者会議をオンラインで開催して試したいです。
「対面で会うのが難しいこの状況下で何ができるか」を考えたときの答えがオンライン会議、慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、ゆっくりと転換していきたいと思います。アイディアをお待ちしています。
*VHO-net(Voluntary Healthcare Organization Network)http://www.vho-net.org/
ヘルスケア関連団体(患者団体・ 障がい者団体・家族団体・支援者団体など)のリーダーや医療福祉関係者たちが、疾病や障がい、立場の違いを越えてフラットにつながっていくことを目指し、ファイザー株式会社が2001年にスタートしたネットワーキングの会。