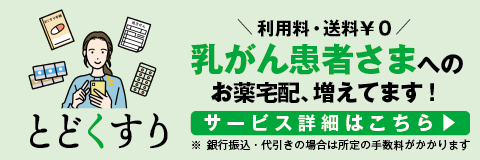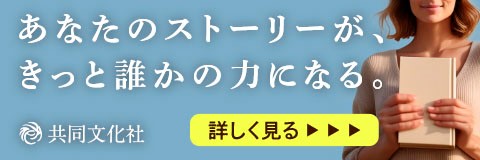「まさか、自分が?」記者が乳がんになったとき 〜患者としての視点から〜
江森美奈子(あけぼの新潟)
(診断)
・2017年1月に会社の人間ドックで精密検査を受けるよういわれ、病院を受診して判明しました。39歳になったばかりでした。少し前に自己触診をしたらベージュ色の分泌物が出たことがあり、気になってドックではオプションのマンモと超音波検査を受けていました。
・マンモでは微細石灰化が左乳房の4分の1くらいに広がっており、先生からはすぐに「悪性なら全摘。でも再建ができる」と言われました。細胞診、組織診を経て「非浸潤がんとみられる」と確定診断を受けました。
(治療)
・手術は3月下旬。左胸の全摘+エキスパンダー挿入と、センチネルリンパ節生検を受けました。病理検査により、当初の見立て通りで、治療は「経過観察のみ」となりました。
・ずっと左胸が痛かったのですが、手術後だから…と思っていました。しかし、手術から1カ月ほどたち、ゴールデンウィーク直前に高熱が出て動けなくなりました。左胸も赤く、病院に駆け込むと、「創部感染」と診断されました。運悪く耐性菌のMRSAが検出され、周囲と接触をしないようにしながら、改善まで2週間入院しました。「異物」を体内に入れるため感染症のリスクが高まると説明を受けてはいましたが、びっくり。病院でもかなり珍しいケースだったようです。その後も微熱や胸が赤くなる症状に悩まされました。
・月1回、エキスパンダーに生理食塩水を入れるための通院を続け、11月末にインプラントと交換する手術を受けました。今は乳腺外科と形成外科にそれぞれ半年に1回ずつ通院しています。
(家族のこと)
・手術当時、2人の息子は小学1年と年中でした。夫をはじめとする家族はもちろん、保育園の先生方や近所のママ友などからもフォローをしてもらってありがたかったです。しかし、入院を繰り返す中で子どもが不安定になっているのかなと思うことがしばしばありました。次男は私の入院以来、目覚めた時に私がいないと不安がる傾向が強くなりました。治療当時、小林麻央さんが乳がんで亡くなりました。「おかあさんも死ぬのではないか」との子どもたちの不安はなかなか消えないようです。
(仕事のこと)
・病気が分かる前、偶然にも地方紙「新潟日報」の記者として、本紙生活面の「がん」をテーマにした長期企画に携わり、多くの患者さんや医療関係者に取材をしてきました(ワット会長はじめ、多くの会員の方にも登場いただきました)。その時の知識や経験がなかったら自己触診もしていなかったし、検診も受けなかったかもしれません。そして、多くの出会いやうかがったお話に、病気に向かうに当たってどれだけ助けていただいたか計り知れません。情報の大切さ、それを伝えることの意味についても考えさせられました。 一方で、取材を重ねてきていても、いざ自分に降りかかったときの衝撃は大きく、どこか「他人事」だったことにはっとさせられました。
・告知からの1年間はトータルで3分の1ほど会社を休まざるを得ませんでした。復帰しても疲れやすく、また体調を崩すのではないかという不安はいつもつきまとっています。会社からも配慮してもらい、体を第一に、なるべく疲れをためないように心がけて生活しています。これからも患者ならではの視点を生かし、紙面を通してがんについての情報を伝えていきたいです。 江森美奈子
*注:江森美奈子さん
江森さんたち新潟日報社報道部社会保障班のがん連載企画は、「第35回ファイザー医学記事賞」の大賞を受賞されました。【あけぼの新潟】の会員も取材に協力し、〈あけぼのハウス〉のことも少し書いていただきました。この記事は「がんと向き合う」という本にまとめられ、新潟日報事業社から発売されています。全国の書店でお取り寄せ可能です。(内藤桂子 記)