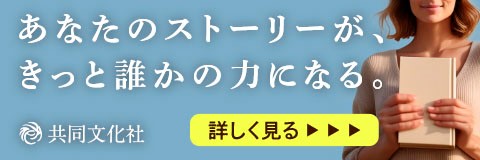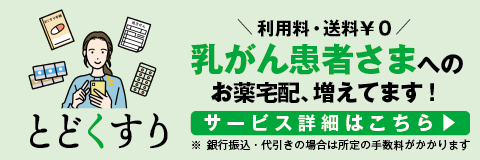共有意思決定“Shared Decision Making(SDM)”
菊井津多子(あけぼの会副会長・あけぼの滋賀代表)《2019年4月29日更新》
 草津総合病院ロビーの五月人形
草津総合病院ロビーの五月人形
撮影:菊井津多子(あけぼの滋賀)
2019/4/23 平成が終わろうとしている今、その長きを振り返る時、先ず思い出すのは15年前のあの場面。2005年5月、『第1回がん患者大集会』の会場だった大阪NHKホールは、全国から集まったがん患者や家族で埋め尽くされていた。
『情報は命です』という会場内の熱い呼びかけに対して、最後に尾辻秀久厚生労働大臣(当時)は官僚が用意したあいさつを脇において、「がん情報センターを設立します」と約束した。がん患者や家族の声が行政トップの心を掴み断言させた、あの瞬間は“これからがん医療は変わる!”と再発治療中の私の心を未来へと繋げてくれた。
その後、2006年に[がん対策基本法]が、2013年に[がん登録推進法]が制定された。2019年4月1日現在、[がん診療連携拠点病院]は全国に392箇所。日本のがん対策は大きく前進した。
が、最近、再発、転移と向き合っているがん患者が治療を選択するのが難しいと感じる場面が多くなっているように思う。どうしたら“患者は治りたい。治してほしい” という思いを医師と共有し、治療選択に反映することができるのだろうか。
先日、再発転移治療4年目の友人とお話をした。薬剤を変え、新薬も試しているがなかなか奏功しない。今回CT検査で他臓器への転移がわかり、「どうして、あの時先生は薬を変えなかったのか? どうして私は『薬を変えてください』と言わなかったのか・・・という後悔が拭えなくて情けなくて」と、とても辛そうだった。そのことを息子さんに話すと、「終わったことを後悔するより、前を向こう。そしてこれからは後悔しないようにしよう」と言われたと。また、緩和ケアの先生にも相談したら、「主治医はもっと後悔していると思いますよ」と言われ、気持ちは少し楽になった。幸いなことに次の薬が効いて体も楽になってきているが、やはり心は晴れない、と。
主治医とのコミュニケーションが足りなかったのか?彼女に患者力がなかったのか?それとも主治医が判断できなかったのかはわからない。ただ言えることは、がん治療は後ろには戻れない。そしてもう二度と後悔しない為には、情報を、思いを、これからの目標を主治医と共有し、共に責任が持てる最良の選択をしてほしい、と思う。
2019年1月に滋賀県で開催されたがん医療フォーラムで特別講演 「共有意思決定“Shared Decision Making(SDM)”とはなにか?」(講師:中山建夫先生/京都大学大学院医学科研究科社会健康医学専攻健康情報学分野教授)を聞いた。これは医療者と患者がエビデンス(科学的な根拠)を共有して一緒に治療方針を決定するという考え方で、まさしく彼女が、がん患者が求めているもの。そして、今のがん医療現場に欠けていることだと思う。
「共有意思決定」は、後悔のない納得した治療を受ける為の考え方のベースとなり、今後患者を支える要になるだろう。 菊井津多子 kikui@crux.ocn.ne.jp